作品データ
原題:37°2 le matin
監督:ジャン=ジャック・ベネックス
原作:フィリップ・ジャン
脚本:フィリップ・ジャン
出演:ベアトリス・ダル、ジャン=ユーグ・アングラード
音楽:ガブリエル・ヤレド
制作:1986年、フランス
あらすじ(ネタバレなし)
肉体労働者として家主にこき使われているゾルグは、ベティというキュートで自由奔放な女と知り合う。
ふたりは夜だけ会って情事を共にするだけの仲だったが、ある日バイトをクビになり、根無草になったベティが昼間ころがりこんできて、そのままベティはゾルグの家で一緒に住むことになる。
ベティはゾルグが家主にこき使われていることを知り、怒って家主の車にペンキをぶちまける。
それでも怒りがおさまらないベティは、ゾルグの家にあるものを次から次へと窓の外から投げ捨て、そのどさくさで、ベティはゾルグが書いた小説を見つける。
ゾルグの小説を読んだベティは感激し、ゾルグに小説を出版社に送って作家になることを勧めるのだった。
ある朝ゾルグと家主が口論をしているとき、ベティは「彼は偉大な作家よ」とわめいて家主をコテージから突き落とす。
そして家に火をつけ、そのままゾルグを連れてパリにいる親友のリザのところへと向かう。
ベティとゾルグ、リザとその恋人エディの4人は楽しい日々を過ごすが、ゾルグの小説はなかなか出版社に受け入れられず、ベティは不満を露わにする。
ベティのヒステリーは次第にエスカレートしてゆくが、ゾルグはベティに変わらぬ愛情をそそぎ続けるのだった。
『ベティ・ブルー 愛と激情の日々(インテグラル版)』の感想
今回初めて3時間のインテグラル版を見た。
120分バージョンは25年くらい前に見たことがあるのだが、ひさしぶりすぎて、どこが追加されたシーンなのかまったくわからず。
しかし冗長な印象はなく、すべてのシーンが無駄なく揃っているように思えた。
最初、ゾルグはなんとなくベティと付き合いはじめる。
夜だけ会う仲だったのが、バイトを辞めて宿無しになったベティが突然、昼間に訪ねてくる。
夜になってイチャイチャしている最中に「ここに住んでいい?」と聞かれて、そのままその場でイチャイチャし続けたいってだけで「いいよ」と答えてしまうゾルグ。
この運命的なカップルが、最初はそんなきっかけなのだ。
この映画は男性ウケしない映画だと聞いたことがある。
ベティが今の言葉でいうメンヘラで、めんどくさい女だから、男に感情移入してもロマンチシズムを感じる以前の問題にぶちあたってしまうからだと想像する。
しかしそれはこの映画の本質を見落とした見解で、ゾルグがベティをそこまで愛す心理には、心が広いとか、それより愛が大きいだとか、そんなこととは次元の違う必然性があるのだ。
↓ここから先はネタバレあり↓
ベティはゾルグが家主にペコペコし、安い賃金で重労働を課されても文句のひとつも言わないのを見かねて激怒し、しまいには家に火をつけて無理やりその生活から脱出させてしまう。
しかしゾルグは重労働のことをベティに隠そうとしていた以上、彼自身もその生活に後ろめたさを感じていたのは確かなのだ。
感情をむき出しに生きるベティは、ゾルグが自分自身についていた嘘さえむき出しにさせるのである。
重要なのはゾルグが家主に500軒ものバンガローのペンキ塗りを命じられ、ベティが怒るシーン。
それと、その直後に、ベティがゾルグの小説を見つけ、徹夜で読みふけるところ。
ペンキ塗りは極めて芸術性から遠い創作物である。
一方、小説は、ゾルグの真の魂が込められた作品なのだ。
この対比。
ゾルグは何軒のバンガローのペンキを塗っても、それは彼の妥協の産物なのである。
ベティはゾルグから嘘の創作物を取り上げ、真の創作物を表に出させる役割を果たす。
そんな女を捨てて、また嘘の自分と付き合い続けることができる男がいるとすれば、それは俗物以外の何者でもない。
その点、ゾルグは純粋な男だったし、ベティも別の意味でピュアな女だったのだ。
だから繰り返して言うが、ベティはめんどくさい女で、ゾルグは心が広くて寛容な男だとか、そんな話しではないのだ。
ベティはゾルグの本当の魂を愛した唯一の女性であり、それを明るい陽の光のもとに連れ出してくれた女性なのである。
この後も少しだらだら書くが、この映画の最大のキーポイントはあくまでもここの部分だということは心に留めておきたい。

ベティ。(出典:imdb)
ここから先はベティの弁護を少し。
こうしてじっくり『ベティ・ブルー』を見ていると、ベティは決して怒りっぽいわけでも、性格がむちゃくちゃなわけでもない。
間際を開けてヒステリーの発作が起きているだけなのだ。
中盤、ベティが逮捕され、引き取りにきたゾルグが刑事に説明するセリフに「Elle a des crises, ça revient chaque mois(あの子は発作持ちなんです。月イチくらいで繰り返すんです)」と言っている。
ベティが家の中のものをかたっぱしに窓から投げ捨てたのも、家に火をつけたのも、レストランで女性客と喧嘩してナイフで腕を刺したのも、きっかけはあったが、発作の一種なんだと思う。
後半、ベティの発作はだんだん頻度が高くなってゆく。
ゾルグが買い物にいくシーンで、ゾルグの声かけに反応もせず黙ってヨガをやっていたかと思うと、買い物が終わったゾルグを車の上で待っているシーンなど、明らかに前半のベティには見られなかった不気味な側面が出はじめている。
前半はだいたいきっかけがあったが、後半は明確な前触れもなく、発作が起きるようになるのだ。
ゾルグがベティの誕生日を祝うシーンは美しい。
しかしラストを知ってから見ると、とても悲しくもある。
ゾルグは最後までベティを心から愛し続けたし、ベティはゾルグを最後まで信じ続けた。
もしゾルグが作家として成功し、ベティは彼の才能を信じて、貧乏だった頃から彼を支えたパートナーとして、ずっとふたりは幸せに暮らす、そんな人生も有りえたかもしれないと思うと、ふたりの日々はちょっと違った風景に見えてくる。
ベティはゾルグに作家になるきっかけを与え、役目を終えて空に帰っていった、天使だったのかもしれない。
こういうのは使い古されたモチーフに思えるし、都合のよい解釈にも聞こえる。
しかしそんな概念にすがりつかないと、悲しくてやりきれないというのがこの映画を見終わった私の正直な心情なのだ。
しかしやはり、悲しい気持ちのもっていきどころは別として、心の底でどこか、「ベティ=天使」の解釈は真理なんじゃないかと本気で信じてしまう自分もいる。
やっぱり私はラストカットが好きだ。
これ以外のラストはありえず、これがあるからベティ・ブルーは名作なのだ。
途中の胸をかき乱されるような切なさも、とりかえしのつかないやるせなさも、このラストがあるから、もう美しい思い出しか残らない。
でもそれはやっぱりどこか悲しくて・・・
しかし奥の奥で満たされてもいる。
そんな不思議な余韻が残る映画だった。
評価
フランス映画で一番好きかもしれない。
★★★★★
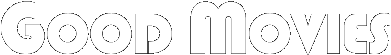




コメント