作品データ
原題:Once Upon a Time in… Hollywood
監督:クエンティン・タランティーノ
脚本:クエンティン・タランティーノ
出演:レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビー、ジュリア・バターズ、デイモン・ヘリマン、マーガレット・クアリー、ダコタ・ファニング、ブルース・ダーン、アル・パチーノ、カート・ラッセル、ゾーイ・ベル
制作:2019年、アメリカ
あらすじ(ネタバレなし)
映画スターを目指す落ち目のテレビ俳優リック・ダルトンと、リックの専属スタントマンであるクリフ・ブースは固い友情で結ばれている。
ある日、映画監督のロマン・ポランスキーと女優のシャロン・テート夫妻が、リックの家の隣に越してきた。
そして1969年8月9日、ある事件が起こる。
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の感想と考察
※この映画は見る前に、「シャロン・テート殺害事件」についてネットで検索して、事件の概要だけでもざっと把握しておくことをおすすめします。
いろんな意味で、いつまでも終わってほしくなかった映画
リックとクリフという2人の架空の人物を通して、1969年のハリウッドを描いている。
つまりわれわれは、リックとクリフに感情移入することで、古き良き時代のハリウッドを追体験できる、という映画である。
いつものタランティーノ映画らしく、ストーリー進行はゆっくりで、かと言って退屈するところは無く、むしろストーリーを急がせるにはもったいない趣に満ちている。
1969年のハリウッドの街並み、車、人間模様、ステキなセリフの数々。
いい映像作品を見ていると、「いつまでも終わらないでほしい」と思うことがあるが、これはそんな映画。
もう、ハリウッドの街並みや人間模様を眺めているだけで楽しくて、ずっと見ていたかった。
しかし一度始まった映画はいつか終わらなければならない。
そしてこの映画が選んだストーリーの題材というのが、1969年に起きたあの忌まわしい事件。
有名女優シャロン・テートが、チャールズ・マンソン率いるヒッピー集団に殺害されたという「シャロン・テート殺害事件」なのだ。
リックとクリフはタランティーノの光と影
映画を見終わってすぐにわかったことだが、主役のリックとクリフはタランティーノ自身なのだ。
タランティーノのナイーブで子供っぽい面がリック。
ワイルドでアダルトな面がクリフである。
リックの役柄が俳優で、クリフの役柄がスタントマン、というところも意味深い。
スタントマンとはいわば俳優の影となる職業。
リックとクリフでひとりの人物の表と裏、という図式がある。
それにふたりの名前も「リック」と「クリフ」、つまり「り」と「く」が逆に入っているのがわかる。
↓ここから先はネタバレあり↓

リックとクリフはタランティーノの分身(出典:amazon)
ある意味これは復讐劇(リベンジ・ムービー)
この映画のラストで、リックとクリフは、シャロン・テートを殺すためにやってきたヒッピーたちを皆殺しにしてしまう。
現実で起きた「シャロン・テート殺害事件」は、この映画の中では未遂に終わるのだ。
つまりこれは、タランティーノは映画というタイムマシーンに乗って、60年代のハリウッドにタイムスリップし、シャロン・テートの隣の家を買い、悪のヒッピー集団からシャロン・テートを救ったのである。
火炎放射は、シャロンを殺すようなヤツらは、地獄の業火に焼かれてしまえ、というタランティーノの怒りの炎なのだ。

死なずに済んだシャロン・テート(出典:imdb)
小説版『その昔、ハリウッドで』から解ること〜タイムパラドックス
前項で私はこの映画はタイムマシーンだと書いたが、タイムマシーンで過去に行って、過去に何かしらの影響を加えるとなると、当然ぶち当たる問題がある。
それがタイムパラドックスだ。
タイムパラドックス(時間の逆説)とは、タイムトラベルで過去に行って現代につながる事象を改変した場合、その事象における過去と現在との、存在や状況に因果関係の不一致が生ずるという、逆説のことを指す。
そしてこのタイムパラドックスの解消ルートには2通りの説があるのだ。
ひとつは、過去に戻って過去を改変すると、「未来が変わってしまう」という説。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』などがこの説に基づいている。
そしてもうひとつは、過去に戻って過去を改変すると、その時点で世界線は2つにわかれ、パラレルワールドが生成される、というもの。
この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のストーリーは、後者の説に基づいて構成されているのである。
この映画によってシャロン・テートが救われた時空が生まれ、この映画が人々に見られる限り、彼女はこの映画の中で生き続けるのだ。
つまり、この映画はもうひとつのハリウッドの有り得た未来につながっているのである。
私はこの映画をタランティーノ自身がノベライズした小説版『その昔、ハリウッドで』を原書で読んだのだが、この小説版を読むと、それがよくわかる。

タランティーノの初小説『その昔、ハリウッドで』。
映画を深く理解したい方には必読の書(出典:amazon)
リックとクリフについてのラストの解釈
さっきリックとクリフはタランティーノ自身だと書いた。
そしてこの2人は、ラストで離れ離れになる。
クライマックスの直前で、リックはクリフに「俺はもうお前を雇う余裕が無い」と打診することで、この2人がもうすぐ一緒にいられなくなることが示唆されるのは実にわかりやすい。
ラスト、クリフは救急車で運ばれ病院に行ってしまい、残されたリックはシャロン・テートに招かれてパーティーに参加する。
これはつまり、大人のタランティーノ(クリフ)は元の未来へと帰ってゆき、子供のタランティーノ(リック)は永遠にこの古き良き時代のハリウッドに生き続ける、という意味なのだ。

リックとクリフ以外で唯一の架空のキャラクター、トゥルーディ・フレイザー
(出典:imdb)
重要なトゥルーディの存在
この、リックは子供の心を持ったタランティーノ自身である、というモチーフを考える上で重要になってくるのが、リックが西部劇TVドラマ『対決ランサー牧場』で共演する8歳の子役トゥルーディ・フレイザーである。
この映画は主役以外はほとんどが実在の人物か、実在の人物にモデルがいる。
その中で、主役のリックとクリフ以外で唯一の架空の人物が、このトゥルーディなのだ。
8歳のトゥルーディがリックより大人っぽく描かれているのは、精神年齢はトゥルーディの方がお姉さんだからである。
タランティーノが自ら執筆したこの映画の小説版では、「シャロン・テート事件」の結末はほとんど描写されず、むしろリックとトゥルーディという、この2人のキャラクターの交流がストーリー上のメインになっている。
小説版のクライマックスは、映画版には無いが、リックがトゥルーディを人質にして悪役ぶりを見せるシーンの撮影の前日に、トゥルーディがリックに「明日は重要なシーンの撮影だからリハーサルをしましょう」と電話をかけてきて、2人が電話ごしにリハーサルをするところなのだ。
そして当日の撮影で、これは映画にあったシーンだが、リックは見事な演技を披露し、撮影後にトゥルーディに耳もとで「わたしが今まで見た中で最高の演技だったわよ」と言われてリックが涙する。
それでは、タランティーノが小説版でここの部分を重要なクライマックスに持ってきた理由とは何か?

小説版ではこのシーンの撮影の前日の2人の電話での会話がクライマックス(出典:imdb)
タランティーノは映画監督より俳優になりたかった
以前タランティーノがインタビューで言っていたことだが、タランティーノは子供の頃、映画監督よりも俳優になりたかったのだそうだ。
この映画の舞台である1969年当時、本物のタランティーノは6歳の子供であったことを思い出すと、これらの断片的な要素がつながるのである。
つまり6歳の頃の、まさにタランティーノが俳優に憧れていた頃そのままの心を持った存在がリックであり、そのリックが自分よりも少しお姉さんのトゥルーディの手ほどきで俳優として一人前になってゆくのが、この映画のもうひとつの重要なストーリーラインになっているのである。
いったんまとめ〜映画はタイムマシーン
先ほどこの映画はタイムマシーンだと書いた。
タランティーノは映画というタイムマシーンを使って、子供の頃の、純粋な気持ちで映画を愛し、俳優を目指していた頃の自分自身の心を、この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』という映画の中に永遠に閉じ込めてしまったのだと言える。
また同時に、子供の頃のタランティーノの心は今でもこの時代に生きている、ということを象徴しているとも言える。
さて、これで私のこの映画の解釈は終わりでいいのだが、最後に余談として、もうちょっと突っ込んだ分析をしてみたい。
タランティーノは何故ブルース・リーを悪く描いたのか
ここからは私の勝手な解釈なので、どうか話半分に聞いてもらえればと思う。
この映画の前半で、まだ有名になる前のブルース・リーが出てきて、クリフに投げ飛ばされてカッコ悪いところを見せてしまうシーンがある。
ブルース・リーのファンには甚だ評判の悪いシーンだが、実はこのシーンでタランティーノが批判したかったのは、中国そのものなのではないかと思う。
タランティーノは中国のカンフー映画は大好きだし、『キル・ビル』で『死亡遊戯』のパロディをやったくらいだから、ブルース・リーは大好きなはずなのだ。
大好きなブルース・リーをわざわざ悪く描くには、ちゃんと意味があるのである。
つまりこの映画のブルース・リーは、ひとつの象徴として使われてしまっただけなのではないかと思うのだ。

わざわざカッコ悪く描かれたブルース・リー(出典:imdb)
タランティーノには不都合なハリウッドの大変革
最近のハリウッドは中国資本が多大に入ってきていて、中国市場を強く意識した作風に大変革を遂げてしまっている。
中国ではダイナミックなCGばかりを使った映画がウケるから、現在のハリウッドはCG全盛期。
CGを使った派手なアクション・スペクタクルばかりが量産されている。
イキなセリフや味のある俳優の演技で魅せる、昔ながらのハリウッド映画はあまり作られなくなってしまった。
そしてタランティーノと言えば、大のCG嫌い、デジタル嫌いで知られる人物だ。
撮影現場にスマホを持ち込むことさえ禁止し、撮影もデジタルカメラは使わず、あくまでもフィルム撮影にこだわり続けている。
この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』も、撮影は従来の35mmフィルムを使用し、1969年の風景もいっさいCGは使わず、しっかりと人間の手で作られたセットと小道具ですべてが再現されている。
タランティーノは、まだハリウッドが人間臭かった1969年の時代を、自分の幼い心とともに、一本の映画という形で閉じ込めたかったのだ。
そしてその永遠に生き続ける1969年のハリウッドに、死んだはずのシャロン・テートも生きている。
そして現実のシャロン・テートを殺したのは、ヒッピーたちなのだ。

CGをいっさい使わず表現された1969年のハリウッドの街並み(出典:imdb)
スパーン映画牧場はハリウッドの縮図
ヒッピーたちはかつて西部劇のロケ地として盛んに使われ、今ではさびれてしまったスパーン映画牧場を、オーナーのジョージ・スパーンに取り入り、自分たちのユートピアとして使わせてもらっている。
ユートピアとはいわゆる共産主義の原型である。
ここでネットで検索して出てきたヒッピー文化の説明文を引用しよう。
ヒッピーとは、1960年代から1970年代前半にアメリカを中心に起こった社会運動。
ヒッピーは、資本主義経済社会を抜け出し、拡張家族として助け合う、ある意味共産主義的な思想を掲げていた。
これを読んでも、一般的な定義で「ヒッピーのコミューンは共産主義的」なものだと考えられているのがわかる。
例えばこの映画の中で、ヒッピーの中に腹ぼての子が何人もいるが、おそらくこの子たちの父親は誰かわからない。
愛と自由とセックスを愛するヒッピーたちは、フリーセックスが基本である。
子宝はここのコミューンの皆の共有財産なのだ。
みんな平等。
食べ物も土地も子供も皆の共有物。
所有権の放棄。
そんな感じのユートピアを、いわば経済的な視点で国家システムとして具現化したものが共産主義なのである。
つまり、かつて映画のロケ現場として栄えたスパーン映画牧場が、ヒッピーたちに侵食されて、半ば共産主義的な世界に毒されている。
この映画におけるスパーン映画牧場の状況は、中国資本びいきになり、人間臭さを忘れてしまった現在のハリウッドの縮図なのである。

スパーン映画牧場の描写は現代のハリウッドの縮図(出典:imdb)
リックがヒッピーを嫌いな理由
小説版『その昔、ハリウッドで』を読むとよくわかるが、ヒッピー集団のリーダーであるチャールズ・マンソンは、理想のユートピアを真面目に実現することなど実は考えておらず、ただミュージシャンとして成功したいために若者たちを洗脳し、利用しているだけの人物として描かれている。
そして現実の共産主義も、経済的な平等を建前に、一部の政治家たちに権力を集中させる悪しき国家システムとしてよく知られているのだ。
小説版にはこのモチーフが実に細かく描かれていて、例えばクリフがスパーン映画牧場を訪れるシーンで、ヒッピーたちはチャールズ・マンソンの留守中にこっそりテレビを見ている。
これはチャールズ・マンソンがヒッピーたちにテレビを見ることを禁止しているからなのだ。
なぜチャールズ・マンソンがヒッピーの仲間たちにテレビを見せたがらないのかというと、テレビのCMを見て物欲が刺激され、ヒッピーたちに外界の豊かな生活などというものに憧れられては困るからだ。
これなどモロに共産主義国家で行われている言論統制と同じである。
タランティーノの分身キャラであるリックは「俺はヒッピーが大嫌いだ!」と、はっきりセリフで言っている。
また、もう一人のタランティーノの分身キャラであるクリフは、スパーン映画牧場を訪れ、ヒッピーたちに利用されすっかり骨抜きにされたジョージ・スパーンと会った後、なんとも言えない失意の表情で「Goddamn it(くそっ!)」と吐き捨てる。
つまり、
ヒッピー=ユートピア=共産主義=中国
| スパーン映画牧場 | ハリウッド |
|---|---|
| かつて映画のロケ地として栄えたが、現在はさびれてヒッピーたちのユートピアになっている | かつて人間味のある映画を撮っていたが、現在は中国市場向けにCGを使った人間味の無いアクション&ファンタジー系の映画ばかりが制作されている |
私の目にはこんな図式が見えてくるのである。

チャールズ・マンソン
彼のユートピア思想を具体化したコミューンは搾取の口実(出典:imdb)
タランティーノ引退宣言の本当の理由
ちなみにタランティーノは10作目を最後に、映画監督を引退すると表明している。
この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は9作目に当たるから、タランティーノの引退宣言が本当だとすると、次の作品が最後、ということになる。
ブルース・リーが大好きなはずのタランティーノがわざわざブルース・リーを悪く描くのには何か重要な理由があるように、映画が大好きなタランティーノがわざわざ、たった10作品で引退を決意するには、おそらく何か重要な理由がある。
その理由はひょっとしたら、ハリウッドが人間味を忘れ、タランティーノの嫌いなデジタル一色のスタイルに塗り替えられてしまった、現在の状況と関係があるのかもしれない。
タランティーノは映画が大好きだが、現在のハリウッドは、タランティーノが大好きだった映画の都とは違ってしまったのだ。

映画を愛する男クエンティン・タランティーノ(出典:imdb)
まとめ
タランティーノは決して政治的な映画作家ではないし、ブルース・リーのシーンからここまで解釈を広げるのは私の勝手な妄想かもしれない。
タランティーノ本人だって、もしこれを読んだら「おいおい、俺の映画をそんなふうに解釈するのはやめてくれよ」と迷惑に思うかもしれない。
だからこの記事の後半は、半分冗談だと思って聞いてもらえたらと思う。
私がこの映画に関してはっきり言えるのは、タランティーノは映画というタイムマシーンに乗って、シャロン・テートの命を救った、ということ。
そして彼はハリウッドにまだ人間味があった1969年という時代を、俳優を目指していた当時の自分の純粋な心とともに、永遠に一本の映画作品という形で閉じ込めておきたかった、ということ。
斯様にこれは、ひとりの映画を愛する男の、夢と憧れと想いが詰まった、ステキな映画なのである。
評価
近年でこんな幸せな気持ちになれた映画はなかった。
★★★★★
Amazonプライムで『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を見る。
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット
『その昔、ハリウッドで』クエンティン・タランティーノ著(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のタランティーノ自身によるノベライズ)
Once Upon a Time in Hollywood: The First Novel By Quentin Tarantino (English Edition) Kindle版
Once upon a Time in Hollywood: A Novel Audible Logo Audible版(オーディオブック)
Once Upon a Time in Hollywood: The Deluxe Hardcover: A Novel(ハードカバー/洋書)
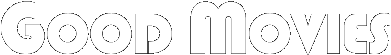




コメント