作品データ
原題:J. Edgar
監督:クリント・イーストウッド
脚本:ダスティン・ランス・ブラック
出演:レオナルド・ディカプリオ、ナオミ・ワッツ、アーミー・ハマー、ジョシュ・ルーカス、ジュディ・デンチ
音楽:クリント・イーストウッド
制作:2011年、アメリカ
あらすじ(ネタバレなし)
初代FBI長官ジョン・エドガー・フーバーは、自身の伝記をスミス捜査官に口述タイプさせている。
彼は司法省の若き官僚として働きはじめ、共産主義者によるパーマー長官襲撃を目の当たりにして己の使命に目覚め、赤狩りの責任者となり、指紋鑑定や筆跡鑑定など科学捜査を積極的に導入し、盗聴を駆使して犯罪防止に務めた。また、秘書のヘレン・ギャンディ、右腕のクライド・トルソンなど部下にも恵まれ、リンドバーグ愛児誘拐事件など有名な事件に多く関わった。
しかし、フーバーの功績の裏には、極めて屈折した別の側面があったのである。
『J・エドガー』の感想
FBIの初代長官。いわゆるFBIを誕生させ、今のような組織に育てた功労者、ジョン・エドガー・フーヴァーの半生を描いた映画。
FBIといえば、アメリカ映画を2本見れば必ずどちらかにはその活躍が見れるようなスゴい組織だが、その成り立ちがよくわかるという点で、とても勉強になる映画でもある。
しかし、それはおまけであって、これはそんな社会科の教科書みたいな映画では決してない。
もちろんイーストウッド監督だから、単なる美談や武勇伝ということもない。
というか、その真逆のようでもある。
そもそもクリント・イーストウッドとは、どんな映像作家であるか。
ストライクゾーンにミットを構えていると、いきなり横っ腹にズドンとデッドボールを喰らって、初めて自分が横を向いていることに気づかされる。
私の中で、ひとくちに言うと、イーストウッドはそんな映画を撮る監督だ。
この映画も、立派な人を描いた映画かと思いきや、FBIの目覚ましい発展の裏に隠された、影の部分をふんだんに描いている。
例えば、ケネディ大統領が東ドイツの女スパイと関係を持ったことを盗聴によって突き止め、ケネディ司法長官を脅し、司法省とFBIとの協力体制を強固なものにしたり。
気に入らない部下を容赦なくクビにしたり。
晩年は嘘で塗り固めた伝記を書かせて、己の功績を誇示したり。
しかしこれらの作為がなかったら、FBIは今のような大きな組織になっていなかった・・・かもしれない。
それからフーバーはゲイで女装趣味でマザコンでもあった。
じゃあこれはフーバーを批判している映画なのかというと、もちろん、そんなせせこましい映画でもない。

ジョン・エドガー・フーヴァー(レオナルド・ディカプリオ)
出典:imdb
フーバーの父は連邦政府の官僚だったが、仕事のストレスか、心を病んで引退。
若い頃から、落ちぶれた父の情けない姿を見て育ち、母に「父に代わって誰よりもこの国で権力をもち、一族を栄光に導いてくれ」と言われて大きくなる。
上司のパーマー長官の襲撃をまのあたりにし(これは嘘っぽいが)、自らの使命に目覚める。
当時はまだその価値をあまり認められていなかった指紋鑑定や筆跡鑑定を取り入れ、科学捜査の精度向上にも尽力した。
ただこれも、局の喫煙室を強引に「ここは今日から科学捜査研究室だ」と言って喫煙者を追い出すなど、無茶な権力行使を行うシーンがある。
いわゆる善悪・虚実・正負の混合。
その表裏一体を体現したような人物だ。
しかしフーバー本人はあくまでもアメリカを敵から守り、国民の幸福と安全を守るため、人生を仕事のみに捧げているつもりでいるらしい。
その強い想いが暴走して、影の部分を太らせることになった、とも言える。
イーストウッドはフーバーという題材のどんなところに魅力を感じてこの映画を作ったのだろうか。

J・エドガー撮影中のクリント・イーストウッド
(出典:imdb)
彼の映画でたびたび目にするモチーフで「Frontier Justice(法に従わない正義)」という言葉がある。
例えばイーストウッドは『グラン・トリノ』という映画で、頑固で無宗教で人嫌いのジイさんが、モン族の家族のホームパーティーに招かれその暖かさにふれた、というだけの縁で、自らの命をなげうってそこの息子を救う様を描いた。
イーストウッドはそういう、法だとか常識だとか民族だとか宗教だとか、そんな枠組みを超えたところでその身を捨てて誰かを守るために悪と戦う人間の魂をこれまでよく描いてきた。
また、私はこの映画を見て、ふとイーストウッドがトランプ大統領について言っていたことを思い出した。
トランプ大統領(当時は候補)の暴言に目くじらをたてる世相を「くだらない。放っておけ」と一蹴し、「軟弱な時代になったもんだ」と吐き捨てる。
「ものごとには必ず両面があるものだ」とも言っている。
確かに言えることは、イーストウッドはフーバーについて肯定も否定もしていない。
FBIを今のような組織に成長させた功績もあれば、脅迫まがいのことをしたり、己のやり方を強引に推し進めたり、嘘をついて己の権力を誇示したり、過ちを覆い隠したりもする。
マザコンでお母さん以外に誰も信じられない歪んだ人間性も描いている。
イーストウッドはそんなフーバーの善悪定からぬ半生を通して、「Frontier Justice」の変化球を放ったのではないか。
そうして、軟弱な現代のアメリカの横っ腹に、フーバーという毒にも薬にもなりそうな人物をズドンとぶつけて、これをまるごと受け止めてみろ、そうした上で今のアメリカを見てみろ、今のアメリカを生きてみろ、そう言っているような気がする。
フーバーを単なる賛否で語る輩は、ズボンの裾にたかる蟻のように、イーストウッドのあのしわくちゃの大きな手でパッパッとはらい落とされておしまいだろう。
私は日本に住んでいる日本人だが、それでもこの映画はガツンと横っ腹に食い込んだ。
肯定も否定もしなくていい。
解釈も分析も考察もいらない。
余計な言葉は必要ない。
ただこのジョン・エドガー・フーヴァーという人物の物語を、腹におさめればそれでいい。
この映画だって所詮は虚構なのだ。
そうした上で、目に映るアメリカが、日本が、世界が、地面の色がどう変わったのか。
そこに映し出された己の度量の深さ、むきだしになった掛け値なしの義勇こそが、この映画の「答え」なのかもしれない。

出典:amazon
評価
イーストウッドのデッドボール、しっかりこの横っ腹で受け止めました。
★★★★★
『J.エドガー (字幕版)』を見る
『J.エドガー (吹替版)』を見る
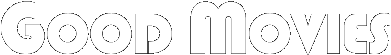



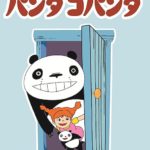
コメント